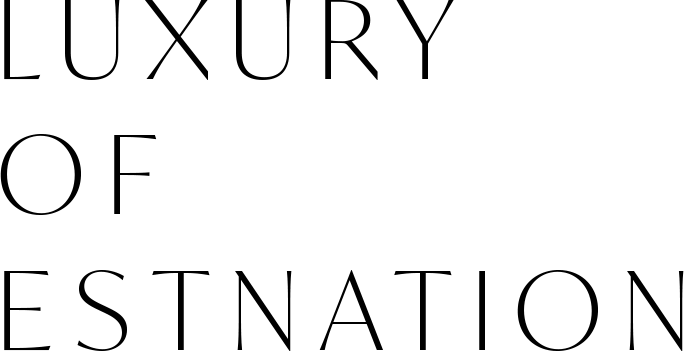ラグジュアリーの本質を追及し、 品質にこだわったものづくりによるタイムレスでクリーンなスタイルを提案する ESTNATION。ただ、そのラグジュアリーの定義とはいったいなんなのか。「豪華な」、「贅沢な」という意味だけで表現することが果たして本質なのか。フリープランナーの種市暁さんを水先案内人とし、それぞれが思い描くラグジュアリーを探す旅に出ます。
Issue 9
松田崇弥挑戦したから味わえる幸福感こそラグジュアリー
ジャンルレスに第一線で活躍する人々に自身のラグジュアリーについて対談を行う連載企画「LUXURY OF ESTNATION」。第9回となるゲストは岩手県盛岡市に本社を置くクリエイティブカンパニー、ヘラルボニーの共同代表の1人である松田崇弥さんが登場。今回の対談はヘラルボニーが7月9日からエストネーション 六本木ヒルズ店にて開催するポップアップイベントに向けて敢行。「異彩を、放て。」というミッションに掲げるヘラルボニーはアートをどのように捉え、発信し、そしてラグジュアリーとどう交わるのか。ポップアップイベントのアイテムの紹介とともにじっくりとお楽しみください。
PROFILE

松田崇弥
1991年岩手県生まれ。東北芸術工科大学卒業後、オレンジ・アンド・パートナーズのプランナーを経験。その後、双子の兄・文登と障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー、ヘラルボニーを設立。
INTERVIEW

1つのアートとして
昇華させたいと思ったのがきっかけ
初めまして。今回は対談を受けていただきありがとうございます。よろしくお願いします。
こちらこそ今日はお越しいただきましてありがとうございます。自己紹介も兼ねてなのですが、ヘラルボニーという会社を運営して今が7年ぐらい。主に知的障害のある作家たちが描いたり、作ったりしたアートワークをデータでライセンシング化して、BtoBとBtoCを軸にその作品たちが繋がるような活動を行っています。いろいろな企業の方々に活用してもらって、障害のイメージを変えることに挑戦しています。岩手の盛岡に本社があり、今日来ていただいた銀座の店と最近パリの方にも子会社ができて、さらに頑張っていこうという状況です。
パリにもあるんですね。僕も前職で鹿児島の障害者支援センターのしょうぶ学園に伺わせていただいたことがあったんですが、その時にあのピュアさというか、表現の力強さに感銘を受けてプロダクトアウトしたいなと思ったことがありました。ただ、そのプロジェクトは色々あって形にはならなかったんですが、今日ショップにお邪魔してみたらちゃんとビジネスになっている。
ありがとうございます。このHERALBONY LABORATORY GINZAは実験的にという形で、今年の3月にオープンしました。我々ってやっぱりアートのデータを著作権管理してIP管理する会社なので、今まで織りとかのようなテクスチャーが入るものっていうのはあまり扱えてなかったんですよね。でも、やっぱり彼らの表現って描くもの以外でも素晴らしいものが沢山あって、編むなどの単純作業にも没頭できる。
わかります。集中力がすごいですよね。
そういったものを低単価ではなく、アートとして昇華させて販売できないんだろうかっていうのが立ち上げのきっかけでした。例えば、さをり織りという織物があるんですが、私が今日着ているシャツも五十嵐さんという作家の作品を洋服に落としこんでいます。
あ、これは実際に織りを作ってもらっているんですね。
そうなんです。1つ1つの織りもルールがなく、フリースタイルでやっていく手法で、コースターやバッグとか、ちょっとした雑貨がよく道の駅などで売られていて見たことがある人もいると思います。そういったものの多くは福祉施設で作られているんですが、また違った場所や目線でも提案できるんじゃないかなと思ったんですよね。
シンプルに素晴らしいじゃないですか。そういった作品たちをもっとファッションの力で面白くしてくというか、皆様の目に触れてもらえる機会が増える。世にあるアートとも対等に評価されるべきだと思うし、そういう活動を行っているってことですよね。
そうなんです。実験的にはなるんですけど、展示や展覧会などいろいろと行っています。
自由なんだけど、色彩のセンスとかいいですよね。僕も仕事でいろんな柄や織りに触れて個性を出そうと一生懸命やってるんですけど、パッションで生み出されたものにはなかなか勝てない。松田さんが着ているものもだし、店内にかかっているシャツも1点1点に個性があって面白いし、美しさを感じます。

ピュアに心のド直球を
表現できるからかっこいい
やはり私たちが作品を描くとなったら、褒められたいなどの承認欲求ってチラつくと思うんですよね。
売れるかなとか。
そうですね。ただ、やっぱり彼らの作品を我々が勝手に作品って呼ばせていただいてるだけで、本人たちは売れるからって気持ちで書いてない。やりたくてやってるという衝動。でも、やっぱり福祉施設の方から褒められるとか、周りの人が認めてくれるとかはもちろん嬉しいと思うんですけど、有名なメディアに取り上げられたり、高値で売れたりすることに欲求はない。だからこそ自由で、私たちには想像のつかない表現が出てくるんだろうなって尊敬しています。
衝動に勝るものはない。夢中になってやってる人の表現力って素晴らしいし、真似ができないですよね。
それでいうと先日、HERALBONY Art Prizeという国際的なアートアワードを行っていて、受賞式があったんですよ。その際、最後に挨拶として作家の皆さんに登壇してもらったんですが、そこで寝始めた方がいた。でも、本人も別にウケを狙ってやってるわけじゃなくて、本当に眠かったから寝る。ピュアに心のド直球を表現できるからかっこいいですよね。ただ、ホテルの支配人には壇上で寝た人は初めてですって言われました(笑)。
嘘がないですからね。僕らは仕事などいろいろな経験をして、フィルターを通しながら生きている。どうしても周りの空気を読んで整えたりすることはできるかもしれないけど、壊すことってなかなかできない。そんなことを気にせずに自分の赴くままにやってるものを見せられると、人はいろいろ考えさせられたり、ハッと思うことがあったりする。なんか俺全然あれだったなみたいな......。今お話しててそういうことのきっかけというか気づきを与えてくれるような活動だなぁと。
いえいえ。まだまだなんですけどね。やはり今はちょっとした閉塞感みたいなものが社会にはあると思うんです。日本では実際8%ぐらい障害のある人たちが手帳を持っていて、知的障害の人たちも100 万人以上存在する。そうなると100人に1 人ぐらいはいるということなんだけど、あんまり可視化されてないんですよね、この社会では。
そうですね。
私の兄も重度の知的障害があるんですけど、謎の言葉を永遠に喋ってたりしていてすごく面白いんですよね。だけど、それが場所によっては怖い人に思われてしまう。実際に兄が叫ぶんで周りからふわーっと人が減ってく光景とかも目にしたことがあるんですが、本人にとってはワクワクする行為の1つだったりもするんですよ。そういうことを知ってもらえるきっかけにESTNATIONのポップアップがなるといいなって思ってます。
エストネーション六本木ヒルズ店のお客様が手に取ったら、どういったリアクションが返ってくるのか楽しみですね。
今回のイベントに参加してくれている中尾涼さんのEMMETIとのレザージャケットも見ましたけど、かなりいい。結構叫びまくって仕上げたアートワークという話を聞いていたので、余計に気合を感じます。あと、もう1つのプロダクトがmarinaさん。ダウン症の作家なんですが、毎日この象形文字のようなアートワークを書かれていて実に不思議なんですよね。ヘラルボニーで原画も販売しているのですが、人気を集めています。
そんなmarinaさんのアートワークをSTATE OF ESCAPEのバッグにプリントしてるんだ。この立体感のあるプリントも雰囲気があって洒落てる。
ともに仕上がりに満足しています。こういったアイテムたちが六本木の素晴らしい場所でお客様がふっと出会ってかっこいいみたいな感じで、作家さんの熱量が届いてくれたらうれしいですね。

ムーブメントを起こす側として、
認識されていく会社でありたい
自分も洋服の仕事をしていて、世界中でさまざまなブランドを見たりとか、物を作ったりしてるんですけど、この年になってくるとただ服着るだけってなんか意味がないと感じることもあるんです。自分の場合はサーフィンやスノーボードをやったりするんでサスティナブルでよかったとか、リカバリーなどの機能がついてるとか、何か意味があるものを選ぶことが増えた。そういう点で言うとヘラルボニーの服には背景がある。実はこういったストーリーがあるんだよっていうのをみんなが発信したくなる服だなと思いました。
そう言っていただけて、うれしいです。実は運動体として認識されていったらうれしいなと思っているんです。例えば、民藝運動で言うと昔ながらの手仕事品には価値がある。民藝なんだっていう言葉を提唱したことによってジャンル化して一気に価値を持ち、市民権を得ました。そう思った時にヘラルボニーも今年の1月時点で国内の福祉施設54カ所、海外4カ所と契約し、契約作家は243名となっています。この活動は僭越ながら民藝運動に近いんじゃないかなと思っているんです。
やはりアートとファッションってリンクしてる部分があると思うんです。ただ、アートだけだとちょっと敷居が高くなることがあるし、プリントTシャツだけだとちょっとしたチャリティ捉えられてしまうこともある。ただ、ヘラルボニーのアイテムはファッションでありながらアートピースでもあるように相乗効果を持って昇華されている。だからムーブメント化が起こって令和の社会活動になる可能性を感じます。言葉はちょっと陳腐かもしれないですけど、最先端のことをやっているなと。
障害のある人の歴史も遡ればいろいろとあるんです。例えば、昔はバスに障害のある人が乗る場合は介助者がいないと乗ってはいけないって法案まであった。それはおかしいだろうということで、無理やり障害のある人たちが10人以上で車椅子で乗り込んだことがあったらしいんです。その超過激派って呼ばれた人たちが実際に存在していて、ニュースを作ることによって同じような声がうわーっと広がる。その声を上げてきた人たちがいるからこそ日本の障害福祉や、海外のノーマライゼーションが成り立った。ただ、今の時代においては障害のある人たちが声高に叫んで、国を批判して、取り上げられるのは理想的ではない。SNSとかもすごく酷似してると思うんですけど、声が大きい人の方が取り上げられてリツイートされますみたいな。そういう座組みにならないことを願っています。
今回の取り組みが自然発生的になっていくきっかけになればいいですよね。それでいうとエストネーションにはその発信力はあるかなと。フラットにいろいろなものがある中で見てもらって、興味を持って気づきが広がっていく。特に六本木ヒルズ店は世界中のセレブの方が買い物しに行くショップなんで。
そうですよね。
言い方はあれかもしれないですけど、セレブリティな方がヘラルボニーのアイテムをかっこいい、面白いって着て、活動が波及していくのっていいですよね。もちろん何であっても言ってくる人もいるけど、本当に強いものは残るし、ピュアに発信している人達の作品って感動する。エストネーションって、ラグジュアリーのバランスの中に新しいものを差し込むのが上手いと思っているんですが、お話を伺ってみてヘラルボニーとの取り組みは面白いことやってきたなって正直思いました。話は変わりますが、ショップはなぜ銀座にしたんですか?
物件は3年ぐらい探してて、出そうと思えば確かに出せはしたんですけど、1店舗目は売れる売れないってよりかはメッセージだと思っていました。どこに1店舗目を構えるかは社会に対して我々はどうなりたいとか、どんな存在として作家と共に歩んでいくかとか、手紙みたいなものだなと。そういったことを考えて場所は妥協したくなかったというのがあり難航しちゃったんですけど、ギャラリーと店舗が2つある場所ができたのはよかった。ファッションもそうですけどやっぱりものを売ってるというよりは、価値観を売る会社でありたいっていうのは思っています。
なるほど。
そういう意味では本当に企業の皆様とも連携しながら、ムーブメントとして広がっていける道筋を探していけるように日々精進しています。あと、会社としてSDGs推しとかにはならないように意識しています。ダイバーシティプロジェクトのヘラルボニーみたいに書かれた場合は赤入れしてて、あまり社会貢献の会社に思われたくないんですよ。シンプルにかっこいい、素敵ってところでふっと入っていける方がファッションにおいて1番いい。ソーシャルとかに逃げずに、ビジュアルとかで勝負できる会社であらないとすぐ潰れるだろうなと。

満ちている人は
素敵だなと思います
この連載ではラグジュアリーについていろいろな方と対談してきたんですけど、豪華とか贅沢なだけじゃなく、形も変わってきていると思うんです。それでいうとこのヘラルボニーの活動は手にすると心が豊かになることを体現している。自分も美術館に行ったり、作品に触れ合ったりする機会はあるんですけれど、それは1つの経験として素晴らしい。そのアーティストの人たちもやっぱりいい意味で常軌を逸してますが。
もちろん。健常者の方の作品もすごいですよね。
みんなもう同じ。シンプルにいいな、面白い、素晴らしいって思って手に入れるっていいことですよね。ちなみに松田さん自身はどのようなことがラグジュアリーだなと思いますか?
それで言うと、何かに挑んでる時って幸福感を最も感じるんですよね。 例えば、ここ最近も英語のピッチの練習をずっとやってたんですよ。仕事の関係でフランスのカンヌで1500名の前で30分間英語で話すことがあって、それは私にとっては本当にチャレンジでして......。
それは大変だ。僕にはできないですね。
私も本当にできるレベルじゃないんですけど......。やっぱり挑戦してるなって時にすごくアドレナリンというか、 その瞬間はきついけど終わったあとの達成感が別格。サウナで整うみたいな感覚というか、挑戦でしか得られないような幸福感を与えてくれる。ラグジュアリーは言葉的に体験や空間とかにお金を払ったものに定義されがちだけど、個人的には成果がどうであっても努力して終わりまでやったことだと思います。実際はそんな努力家でもないんですけど(笑)。
普段は生活してて、自分はラグジュアリーだなって思わないですもんね。考えないところはあるかもしれないけど、充足感は豊かでラグジュアリーという定義になる。
客観的に満ちてる人は素敵だなと思いますよね。
いろいろなブランドがあるけど、ネームで選ぶのではなく、本質を見抜くことが大事だと思うんです。そういう心が豊かな人が今回のポップアップイベントで買ってくれるといいですよね 。決してどっちを買わなきゃダメとかっていう話じゃないじゃないですか。自分もフラットに見て心の持ちようで判断できたらいいなと思うし、豊かさなんじゃないのかなぁなんて。
素晴らしいコメントだったのでぜひ使ってください(笑)。本当にその通りだなと思いました。
ありがとうございます(笑)。あと余談ですが、古着ってやっぱり一点物の面白さってあるじゃないですか。 見つけたりするのが好きで、価値の決め方っていうのも面白いんですよ。なんでこれでこんなにすんのみたいな。
深い世界ですよね。
もうボロボロになってるTシャツにすごいカタルシスを感じて、 めちゃくちゃかっこいいみたいな。そういうものの佇まいというか、ヘラルボニーのシャツやポップアップイベントに出るアイテムも使っていってボロボロになっていったらさらにかっこよくなると思うんですよ。
あ、逆にですね。
10年ぐらい経って、補修しながら着ていったらより雰囲気が出そう。
確かにパッチとかつけてたらかっこいいですよね。自分でもやりたいです。
ただでさえ個性があるのに、自分のものになっていって、唯一無二になる。自分の歴史も入っていくことの面白さがあるから、未来のヴィンテージとしても楽しみですね。
本当ですか。未来のヴィンテージになれるように今後も頑張っていきます。
「HERALBONY JOURNEY」
2025年7月9日(水)〜 7月31日(木)の期間、エストネーション六本木ヒルズ店にて、ヘラルボニーによるポップアップストアを開催。本イベントでは、アートを纏うことが日常の中で感性を解き放つきっかけとなるような体験を提案します。「異彩を、放て。」をテーマに、複数のアーティストによる原画展示やライブペインティング。
さらには今回のポップアップストア限定で、ヘラルボニー契約作家であるmarina氏による作品(marina moji)を、STATE OF ESCAPEの人気モデルに落とし込んだアイテムの販売や、アーティストの中尾涼氏とイタリア発のラグジュアリーアウターブランドEMMETIによるコラボレーションレザーJKオーダー会を開催するなど、多彩なコンテンツを展開いたします。
※ライブペインティングに関して
2025年7月12日 (土) 14:00 ~ 16:00
marinaによるライブペインティングイベントを開催。
その場で生まれる異彩の瞬間を、ぜひご体感ください。
NAOKI WASHIZU
AKIRA TANEICHI
YUMA YOSHITSUGU
KEI MATSUO (TEENY RANCH)